”にしきたショパン”・・・久々の映画鑑賞。 ― 2023年04月04日

さくらウオーク後片付けを終えていったん帰宅し、3時過ぎに再び山口ホールに向かった。3時半から上映される映画「にしきたショパン」を観るためだ。
この作品の主演女優・水田汐音さんとはちょっとした関りがあった。2014年に同じ山口ホールで上演された「ミュージカル・有間皇子物語」の幼少期を演じたのが当時13歳の名塩出身の水田さんだった。私はその公演を主催した劇団・希望の後援会事務局長だった。そんな縁もあり、また身近なホールでの興味深い作品ということもあって会場に足を運んだ。
ホールに足を踏み入れた。会場は7割方の観客で占められていた。上映に先立ってプロデューサー・近藤修平氏と監督・竹本祥乃氏によるトークショーが始まった。この作品が誕生する経過や主演二人のプロフィール、作品のみどころなどが分かりやすく紹介された。
上映が始まった。水田さん演じるヒロイン凜子が登場する。かつての幼さの残った面影は窺えない。国際ピアノコンクールで1位を取ったピアニストであり、モデルでもある西宮出身の22歳の女優である。トークショーで監督が”この作品のために生まれたような女性”というコメントそのものである。幼なじみの鍵太郎とのピアニストとしての葛藤がメインのテーマのようだ。全体にモノクローム調の映像と抑制されたセリフが基調となって展開する。
タイトルの「にしきたショパン」は文字通りこの作品のキーワードである。言うまでもなく”にしきた”とは阪急電車の西宮北口駅界隈である。舞台の多くがこの界隈で展開される。ショパンという作曲家をこの作品を通じてあらためて知った。ショパンはピアノとピアノ曲にこだわり続けたピアニストであり作曲家である。ピアニストたちにとって最高のあこがれの人物なのだろう。
久々の映画鑑賞の心にしみた感傷に浸りながら会場を後にした。
この作品の主演女優・水田汐音さんとはちょっとした関りがあった。2014年に同じ山口ホールで上演された「ミュージカル・有間皇子物語」の幼少期を演じたのが当時13歳の名塩出身の水田さんだった。私はその公演を主催した劇団・希望の後援会事務局長だった。そんな縁もあり、また身近なホールでの興味深い作品ということもあって会場に足を運んだ。
ホールに足を踏み入れた。会場は7割方の観客で占められていた。上映に先立ってプロデューサー・近藤修平氏と監督・竹本祥乃氏によるトークショーが始まった。この作品が誕生する経過や主演二人のプロフィール、作品のみどころなどが分かりやすく紹介された。
上映が始まった。水田さん演じるヒロイン凜子が登場する。かつての幼さの残った面影は窺えない。国際ピアノコンクールで1位を取ったピアニストであり、モデルでもある西宮出身の22歳の女優である。トークショーで監督が”この作品のために生まれたような女性”というコメントそのものである。幼なじみの鍵太郎とのピアニストとしての葛藤がメインのテーマのようだ。全体にモノクローム調の映像と抑制されたセリフが基調となって展開する。
タイトルの「にしきたショパン」は文字通りこの作品のキーワードである。言うまでもなく”にしきた”とは阪急電車の西宮北口駅界隈である。舞台の多くがこの界隈で展開される。ショパンという作曲家をこの作品を通じてあらためて知った。ショパンはピアノとピアノ曲にこだわり続けたピアニストであり作曲家である。ピアニストたちにとって最高のあこがれの人物なのだろう。
久々の映画鑑賞の心にしみた感傷に浸りながら会場を後にした。
映画「痛くない死に方」 ― 2021年03月12日

敬愛する町医者・長尾医師原作の映画「痛くない死に方」を観た。3年前に原作を読んでいた。原作では特に「痛くない死に方には緩和医療の知識と理解のあるかかりつけ医を見つけておくこと。緩和ケアがしっかりできないと在宅看取りには至らない。それにはかかりつけ医の在宅看取り数が目安となる」といったことを学んだ。この映画のテーマもせんじ詰めればその点を映像化したものと思えた。
物語は前半と後半に二人の末期の癌患者の終末期医療の進行の様子を描きながら展開する。若い在宅医師の河田(柄本佑)が二人の在宅医療を担当する。前半のクライマックスでは、末期肺癌の父親を自分の意向で自宅で介護することを選択した娘の想いが河田に突き刺さる。“痛くない在宅医”を選んだはずなのに、結局“痛い在宅医”だったという非難の言葉だった。
後半は、河田が2年後に担当することになった末期の肝臓がん患者である本多彰(宇崎竜童)の終末期医療の物語である。前半とは打って変わり自信を持って患者と向き合う河田が登場する。ジョークと川柳が好きで、末期がんの患者とは思えない明るい本多と、明るく寄り添う妻・しぐれ(大谷直子)との触れ合いに心和まされる。河田が勤務するクリニック院長・長野(奥田英二)の「カルテでなく人を見ろ」という言葉が生きている。そして本多は、河田や妻に看取られながら自宅で見事な「痛くない死に方」を全うする。
本多の終末期の楽しみだった終末川柳が興味深かった。記憶に残った二句を記しておく。
「まるはげの 主治医が勧める 抗がん剤」「自尊心 紙のおむつが
踏みつぶす」
物語は前半と後半に二人の末期の癌患者の終末期医療の進行の様子を描きながら展開する。若い在宅医師の河田(柄本佑)が二人の在宅医療を担当する。前半のクライマックスでは、末期肺癌の父親を自分の意向で自宅で介護することを選択した娘の想いが河田に突き刺さる。“痛くない在宅医”を選んだはずなのに、結局“痛い在宅医”だったという非難の言葉だった。
後半は、河田が2年後に担当することになった末期の肝臓がん患者である本多彰(宇崎竜童)の終末期医療の物語である。前半とは打って変わり自信を持って患者と向き合う河田が登場する。ジョークと川柳が好きで、末期がんの患者とは思えない明るい本多と、明るく寄り添う妻・しぐれ(大谷直子)との触れ合いに心和まされる。河田が勤務するクリニック院長・長野(奥田英二)の「カルテでなく人を見ろ」という言葉が生きている。そして本多は、河田や妻に看取られながら自宅で見事な「痛くない死に方」を全うする。
本多の終末期の楽しみだった終末川柳が興味深かった。記憶に残った二句を記しておく。
「まるはげの 主治医が勧める 抗がん剤」「自尊心 紙のおむつが
踏みつぶす」
JAのなんばグランド花月観劇と黒門市場散策ツアー ― 2018年06月29日
JA兵庫六甲に年金口座を持っている。その年金受給者対象のバスツアーの案内があった。行先はなんばグランド花月の観劇と黒門市場のショッピングで、お弁当の昼食付き6500円というお手軽ツアーである。早速、ご近所のご夫婦と一緒に申込んだ。
ツアー当日の朝9時、住宅街のコミセン前をツアーバスが出発した。なんばグランド花月近くの車道でバスを降り歩いて数分の劇場前に到着。10時20分にはバス2台56名の参加者が添乗員からチケットとお弁当を受取って開場した劇場に入場した。渡されたチケット番号G14は1階席の前から7列目中央の絶好の観劇席だった。
11時の開演前に若手芸人たちのショーを観た後、いよいよ開演を迎えた。11時から12時半までの前半は、5組の漫才と各1組の落語、ジャグリング、コントが演じられた。漫才では海原やすよともこを筆頭に若手のアインシュタインが楽しめた。ベテラン勢ではのWヤングが頑張っていると思えたが、大木こだまひびきのマンネリ感と中田カウス・ボタンの嫌味な芸風に眠気を誘われた。若手パフォーマーのもりやすバンバンビガロのジャグリングや桂小枝の落語もなかなかのもので楽しめた。坂田利夫メインのコントは笑えないギャグ乱発のスタイルで退屈だった。
前半終了後の休憩中にプラスチックの専用弁当箱「吉本大笑い弁当」に盛り付けられたお弁当を食べた。芸人たちの似顔絵をあしらった弁当箱がウリの平凡な料理だった。
後半の45分は6人の座長がプロデュースした喜劇を毎週交替で演じる吉本新喜劇である。今回の座長はおかっぱ頭のメガネ巨乳で大阪のおばちゃんイメージの「すっちー」だった。池乃めだかも出演する「すち子の、夢を叶えるギター」という喜劇だったが、ギャグ中心のドタバタ劇自体に馴染めないこともありイマイチ楽しめなかった。
NGKから歩いて数分の黒門市場を散策した。鮮魚店を中心に青果店や精肉店など約150店が軒を連ねる「大阪の台所」である。最近はコロッケ、から揚げ、焼き魚、寿司、お造りなどが店頭で味わえる食べ歩きが人気の観光スポットに変貌している。実際に南北のアーケードをアジア系の外国人を中心に大勢の観光客が闊歩している。食べ歩きのメニューをみると総じて高い。財布の紐が緩い観光客相手の書かう設定が透けてみえる。50分ばかりの散策時間を持て余し、休憩スポットで500円アイスを食べながら時間を潰した。
15時10分の集合時間を待ってバスに乗り込み帰路についた。16時には住宅街の出発地に到着し、リーズナブルなお手軽ツアーを終えた。
ツアー当日の朝9時、住宅街のコミセン前をツアーバスが出発した。なんばグランド花月近くの車道でバスを降り歩いて数分の劇場前に到着。10時20分にはバス2台56名の参加者が添乗員からチケットとお弁当を受取って開場した劇場に入場した。渡されたチケット番号G14は1階席の前から7列目中央の絶好の観劇席だった。
11時の開演前に若手芸人たちのショーを観た後、いよいよ開演を迎えた。11時から12時半までの前半は、5組の漫才と各1組の落語、ジャグリング、コントが演じられた。漫才では海原やすよともこを筆頭に若手のアインシュタインが楽しめた。ベテラン勢ではのWヤングが頑張っていると思えたが、大木こだまひびきのマンネリ感と中田カウス・ボタンの嫌味な芸風に眠気を誘われた。若手パフォーマーのもりやすバンバンビガロのジャグリングや桂小枝の落語もなかなかのもので楽しめた。坂田利夫メインのコントは笑えないギャグ乱発のスタイルで退屈だった。
前半終了後の休憩中にプラスチックの専用弁当箱「吉本大笑い弁当」に盛り付けられたお弁当を食べた。芸人たちの似顔絵をあしらった弁当箱がウリの平凡な料理だった。
後半の45分は6人の座長がプロデュースした喜劇を毎週交替で演じる吉本新喜劇である。今回の座長はおかっぱ頭のメガネ巨乳で大阪のおばちゃんイメージの「すっちー」だった。池乃めだかも出演する「すち子の、夢を叶えるギター」という喜劇だったが、ギャグ中心のドタバタ劇自体に馴染めないこともありイマイチ楽しめなかった。
NGKから歩いて数分の黒門市場を散策した。鮮魚店を中心に青果店や精肉店など約150店が軒を連ねる「大阪の台所」である。最近はコロッケ、から揚げ、焼き魚、寿司、お造りなどが店頭で味わえる食べ歩きが人気の観光スポットに変貌している。実際に南北のアーケードをアジア系の外国人を中心に大勢の観光客が闊歩している。食べ歩きのメニューをみると総じて高い。財布の紐が緩い観光客相手の書かう設定が透けてみえる。50分ばかりの散策時間を持て余し、休憩スポットで500円アイスを食べながら時間を潰した。
15時10分の集合時間を待ってバスに乗り込み帰路についた。16時には住宅街の出発地に到着し、リーズナブルなお手軽ツアーを終えた。
関口祐加監督「毎日がアルツハイマー1・2」 ― 2018年04月30日
認知症を発症した母親の介護の日々を映像で綴ったドキュメンタリー映画「毎日がアルツハイマー」のDVD2巻を購入し観賞した。認知症関係者の間では知る人ぞ知る著名な作品で、かねてからぜひ観賞したいと思っていたものだ。
第1巻は、監督である関口祐加氏が79歳の母親の認知症発症を機に滞在中のオーストラリアから帰国し、2年半に及ぶ「毎日がアルツハイマー」の介護の日々を動画で納めたものだ。現在進行形の認知症介護の生々しい現実を泣き笑いをこめたリアリティ溢れるタッチで追っている。
第2巻は、前作から2年を経て83歳を迎えた母親の閉じこもり生活からの変化を伝えるシーンから始まる。デイサービスに通い始め、嫌がっていた洗髪を受入れ、監督である娘と外出もする。反面、感情の起伏が激しく突然怒りだしたり一日中ベッドに引きこもることも。そんな時、娘は「パーソン・センタード・ケア(認知症本人を尊重するケア)」という言葉に出会い、自らその最先端の認知症介護の在り方を知るためにイギリスに渡る。本人の人柄、人生、心理状態を探り、ひとりひとりに適切なケアを導き出す介護の実践の現場を体験する。
認知症介護という将来訪れるかもしれない現実に多くの人が不安を抱いているだろう。この作品はその認知症介護のありのままの生々しい現実を映像を通して教えてくれる。当事者と介護者が母親と実の娘という関係の介護生活である。言いたいことを言い合える関係だけに救いがあるという一面があるのかもしれない。それでもきれいごとでない等身大の視線での映像化は、ベールに包まれた不安感を取り除き観るものにある種の安心感をもたらしてくれる。
第1巻は、監督である関口祐加氏が79歳の母親の認知症発症を機に滞在中のオーストラリアから帰国し、2年半に及ぶ「毎日がアルツハイマー」の介護の日々を動画で納めたものだ。現在進行形の認知症介護の生々しい現実を泣き笑いをこめたリアリティ溢れるタッチで追っている。
第2巻は、前作から2年を経て83歳を迎えた母親の閉じこもり生活からの変化を伝えるシーンから始まる。デイサービスに通い始め、嫌がっていた洗髪を受入れ、監督である娘と外出もする。反面、感情の起伏が激しく突然怒りだしたり一日中ベッドに引きこもることも。そんな時、娘は「パーソン・センタード・ケア(認知症本人を尊重するケア)」という言葉に出会い、自らその最先端の認知症介護の在り方を知るためにイギリスに渡る。本人の人柄、人生、心理状態を探り、ひとりひとりに適切なケアを導き出す介護の実践の現場を体験する。
認知症介護という将来訪れるかもしれない現実に多くの人が不安を抱いているだろう。この作品はその認知症介護のありのままの生々しい現実を映像を通して教えてくれる。当事者と介護者が母親と実の娘という関係の介護生活である。言いたいことを言い合える関係だけに救いがあるという一面があるのかもしれない。それでもきれいごとでない等身大の視線での映像化は、ベールに包まれた不安感を取り除き観るものにある種の安心感をもたらしてくれる。
映画「インビクタス/負けざる者たち」 ― 2014年11月05日
先日、BS-TBSで放映された映画「インビクタス/負けざる者たち」の録画を観た。久々に見応えのある余韻の残る映画だった。27年に及ぶ投獄生活を経て南アフリカ大統領に就任したネルソン・マンデラの就任直後の民族和解の奮闘を描いたものである。
大統領就任直後、マンデラは初登庁の日に前政権のスタッフだった白人職員を集めて呼びかける。「辞めるのは自由だが、新たな南アフリカを作るために協力してほしい。あなたたちの力が必要だ」。白人政権によるアパルトヘイトで長期に投獄され数々の障害まで負ったマンデラの民族融和の呼びかけである。アパルトヘイト体制下での国際社会からの経済制裁や人種間対立、民族間対立で疲弊しきった国を再生する上で民族融和は何としても成し遂げなければならないテーマだった。高い志を持って困難を乗り越えようとする強い意志に支えられたマンデラの呼掛けに多くの職員が同意する。
マンデラは側近たちの反対を押し切って、ラグビーというアパルトヘイトの象徴的なスポーツの南アフリカ代表チームを全面的に支援する。自国で開催されたワールドカップで代表チームが見事に決勝戦を制した時、南アフリカは初めて人種や民族を超えた一体感を共有する。
マンデラが繰り返し口にする詩が印象的だった。「我が運命を決めるのは我なり、我が魂を制するのは我なり」。超越した克己心をもって苛酷な運命を切り開いた不屈の精神の呟きである。「負けざる者たち」の原点というべきか。
民族対立が激化している。ちまたで、ネット上で、傍若無人なヘイトスピーチが横行し、民族対立を煽っている。そんな状況下でのこの作品の観賞だった。ネルソン・マンデラの崇高な精神を噛み締めた。
大統領就任直後、マンデラは初登庁の日に前政権のスタッフだった白人職員を集めて呼びかける。「辞めるのは自由だが、新たな南アフリカを作るために協力してほしい。あなたたちの力が必要だ」。白人政権によるアパルトヘイトで長期に投獄され数々の障害まで負ったマンデラの民族融和の呼びかけである。アパルトヘイト体制下での国際社会からの経済制裁や人種間対立、民族間対立で疲弊しきった国を再生する上で民族融和は何としても成し遂げなければならないテーマだった。高い志を持って困難を乗り越えようとする強い意志に支えられたマンデラの呼掛けに多くの職員が同意する。
マンデラは側近たちの反対を押し切って、ラグビーというアパルトヘイトの象徴的なスポーツの南アフリカ代表チームを全面的に支援する。自国で開催されたワールドカップで代表チームが見事に決勝戦を制した時、南アフリカは初めて人種や民族を超えた一体感を共有する。
マンデラが繰り返し口にする詩が印象的だった。「我が運命を決めるのは我なり、我が魂を制するのは我なり」。超越した克己心をもって苛酷な運命を切り開いた不屈の精神の呟きである。「負けざる者たち」の原点というべきか。
民族対立が激化している。ちまたで、ネット上で、傍若無人なヘイトスピーチが横行し、民族対立を煽っている。そんな状況下でのこの作品の観賞だった。ネルソン・マンデラの崇高な精神を噛み締めた。
榛名由梨主演・ミュージカル「永遠物語」 ― 2013年04月05日
昨日、宝塚大劇場・バウホールで上演されている榛名由梨舞台生活50周年記念ミュージカル「永遠物語」(原作・無法松の一生)を観劇した。市民ミュージカル劇団『希望』後援会の役員お二人が一緒だった。
昨年4月の後援会主催のシンポジュウムにパネラーのひとりとして榛名由梨さんに無償出演してもらった。その気さくで明るいトークが好評だった。個人的にもご近所にお住まいで顔を合わせれば挨拶を交わし合う。そんな榛名さんの記念すべき今回の公演だった。これは観ないわけにはいかない。
11時開演のバウホールには中年のご婦人を中心に7割方の観客が席を占めた。高齢おじさん三人組も11列目の正面に着席した。500席のホールは思った以上に舞台との一体感がある。25分間の幕間休憩を挟んで3時間近い舞台だった。
舞台芸術のレベルの高さに圧倒された。榛名さんが50年に渡る舞台生活で培われた円熟の熱演で松五郎を演じきった。花總(はなふさ)まりさん演じる吉岡夫人の美しさと上品な語り口にしばしば息を呑んだ。大勢の出演者が織りなすダンスシーンもミュージカルのもつスピード感と迫力をいかんなく発揮していた。演劇専用の広さと機能を備えた舞台はさすがだった。多彩な照明装置を駆使した光の造形が舞台演出を盛り上げていた。ホールの音響効果の高さと相俟って音響設備もまた素晴らしいサウンドを提供した。大道具などの舞台造りの凄さは同行者が一致して認めるところだった。剥き出しの2階建の鉄パイプの骨組みが、場面に応じて様々な大道具、小道具を付加して変幻自在にシーンを展開した。あらためて舞台芸術が総合芸術であることを実感した。
これだけの舞台公演に要する費用の膨大さを想った時、全席指定のチケット料金8千円も納得できた。今回の公演は8日間、12回の舞台である。定員の平均8割の観客としても入場料収入は3840万円である。これで企画・広告費、原作・脚本・作曲費、ホール使用料、舞台製作費、舞台衣装代、音響・照明費用、スタッフ人件費、俳優出演料、その他諸々の費用負担を賄うわけである。
我が市民ミュージカル劇団『希望』も11月末に、創作ミュージカル「有間皇子物語」の公演を予定している。「永遠物語」を観終えてその素晴らしさを噛みしめながら、他方で「有間皇子物語」の資金調達の厳しさに想いをいたした。
昨年4月の後援会主催のシンポジュウムにパネラーのひとりとして榛名由梨さんに無償出演してもらった。その気さくで明るいトークが好評だった。個人的にもご近所にお住まいで顔を合わせれば挨拶を交わし合う。そんな榛名さんの記念すべき今回の公演だった。これは観ないわけにはいかない。
11時開演のバウホールには中年のご婦人を中心に7割方の観客が席を占めた。高齢おじさん三人組も11列目の正面に着席した。500席のホールは思った以上に舞台との一体感がある。25分間の幕間休憩を挟んで3時間近い舞台だった。
舞台芸術のレベルの高さに圧倒された。榛名さんが50年に渡る舞台生活で培われた円熟の熱演で松五郎を演じきった。花總(はなふさ)まりさん演じる吉岡夫人の美しさと上品な語り口にしばしば息を呑んだ。大勢の出演者が織りなすダンスシーンもミュージカルのもつスピード感と迫力をいかんなく発揮していた。演劇専用の広さと機能を備えた舞台はさすがだった。多彩な照明装置を駆使した光の造形が舞台演出を盛り上げていた。ホールの音響効果の高さと相俟って音響設備もまた素晴らしいサウンドを提供した。大道具などの舞台造りの凄さは同行者が一致して認めるところだった。剥き出しの2階建の鉄パイプの骨組みが、場面に応じて様々な大道具、小道具を付加して変幻自在にシーンを展開した。あらためて舞台芸術が総合芸術であることを実感した。
これだけの舞台公演に要する費用の膨大さを想った時、全席指定のチケット料金8千円も納得できた。今回の公演は8日間、12回の舞台である。定員の平均8割の観客としても入場料収入は3840万円である。これで企画・広告費、原作・脚本・作曲費、ホール使用料、舞台製作費、舞台衣装代、音響・照明費用、スタッフ人件費、俳優出演料、その他諸々の費用負担を賄うわけである。
我が市民ミュージカル劇団『希望』も11月末に、創作ミュージカル「有間皇子物語」の公演を予定している。「永遠物語」を観終えてその素晴らしさを噛みしめながら、他方で「有間皇子物語」の資金調達の厳しさに想いをいたした。
映画「草原の椅子」 ― 2013年03月16日
先日の大阪市大病院の半年ぶりの診察の日のことだ。11時半の診察の後、5時からの労働委員会の定例会までたっぷり空き時間があった。前日にネットで大阪ステーションシネマの12時25分上映の「草原の椅子」を予約した。
市大病院の受診科待合室には担当医師の診察状況がディスプレイに表示される。到着して確認すると、なんと60分遅れの表示だった。大幅な上映時間遅れを気にしながら待つこと60分、ようやく診察室に呼ばれた。先週の腫瘍マーカー検査の結果を聞いた。問題なしとのことだった。手術後6年を経過し異常は認められず、今後は半年に1回のCT検査だけで良いとのことだった。
大阪ステーションシネマには1時20分に着いた。2時間20分の上映時間の半ば近くが過ぎていた。最初に目に入ったのは、ともに50歳の遠間(佐藤浩市)と富樫(西村雅彦)とアラフォーの美しい女性・貴志子(吉瀬美智子)がカウンターバーで飲んでいるシーンだった。前半の経過が分からないまま、この三人に4歳の少年・圭輔を中心にストーリーが展開する。三人の大人たちは、それぞれに様々な葛藤を抱え苦悩を背負って生きている。母親に虐待され心に傷を負い正常な言葉を失った圭輔を、それぞれの苦悩を通して理解し見守ろうとする。遠間と富樫の中年過ぎの友情や、遠間と貴志子の大人の控え目な恋を絡めて、4人は世界最後の桃源郷と呼ばれるパキスタン・フンザへ旅立つ。大自然の砂漠に身を置き、現地の長老の言葉を聞きながら、遠間と貴志子は圭輔との新しい家族をつくることを決意する。
家族や地域や職場での絆の希薄化・崩壊が語られて久しい。東日本大震災で多くの人々の家族が崩壊し、地域の繋がりが寸断した。旧来の日本的な人と人の関わり方の根底が揺らいでいるのだろうか。この作品はそんな時代状況の中で、あらたな関わり方の姿を描いているかにみえる。大自然を媒介にしながら、自分自身に素直になることからしか出発するほかはない。そんな素朴なメッセージが伝わる。
それにしても女優・吉瀬美智子の美しさと演技力を実感させられた。30代でモデルから転身し今やアラフォーの遅咲き女優である。佐藤浩市や西村雅彦といった実力派俳優たちに伍して見事に清楚で芯の強い役柄をこなしていた。前半を観れなかった不完全燃焼感はあったものの、初めての吉瀬美智子の出演作品に癒された。
市大病院の受診科待合室には担当医師の診察状況がディスプレイに表示される。到着して確認すると、なんと60分遅れの表示だった。大幅な上映時間遅れを気にしながら待つこと60分、ようやく診察室に呼ばれた。先週の腫瘍マーカー検査の結果を聞いた。問題なしとのことだった。手術後6年を経過し異常は認められず、今後は半年に1回のCT検査だけで良いとのことだった。
大阪ステーションシネマには1時20分に着いた。2時間20分の上映時間の半ば近くが過ぎていた。最初に目に入ったのは、ともに50歳の遠間(佐藤浩市)と富樫(西村雅彦)とアラフォーの美しい女性・貴志子(吉瀬美智子)がカウンターバーで飲んでいるシーンだった。前半の経過が分からないまま、この三人に4歳の少年・圭輔を中心にストーリーが展開する。三人の大人たちは、それぞれに様々な葛藤を抱え苦悩を背負って生きている。母親に虐待され心に傷を負い正常な言葉を失った圭輔を、それぞれの苦悩を通して理解し見守ろうとする。遠間と富樫の中年過ぎの友情や、遠間と貴志子の大人の控え目な恋を絡めて、4人は世界最後の桃源郷と呼ばれるパキスタン・フンザへ旅立つ。大自然の砂漠に身を置き、現地の長老の言葉を聞きながら、遠間と貴志子は圭輔との新しい家族をつくることを決意する。
家族や地域や職場での絆の希薄化・崩壊が語られて久しい。東日本大震災で多くの人々の家族が崩壊し、地域の繋がりが寸断した。旧来の日本的な人と人の関わり方の根底が揺らいでいるのだろうか。この作品はそんな時代状況の中で、あらたな関わり方の姿を描いているかにみえる。大自然を媒介にしながら、自分自身に素直になることからしか出発するほかはない。そんな素朴なメッセージが伝わる。
それにしても女優・吉瀬美智子の美しさと演技力を実感させられた。30代でモデルから転身し今やアラフォーの遅咲き女優である。佐藤浩市や西村雅彦といった実力派俳優たちに伍して見事に清楚で芯の強い役柄をこなしていた。前半を観れなかった不完全燃焼感はあったものの、初めての吉瀬美智子の出演作品に癒された。
映画「マディソン郡の橋」 ― 2013年03月10日

テレビで放映され録画していた映画「マディソン郡の橋」を観た。18年前に封切られた映画である。その2~3年後にテレビで放映されて観た時の好印象が残っていた。最近またBS朝日で放映されたのを知って録画しておいた。大筋のストーリーはほぼ記憶に残っていたが、個々のシーンでは新鮮な受け止め方で共感しながら愉しんだ。
この作品が取上げたテーマについての評価は大きく分かれている。「単に不倫を美化しただけの作品」という否定的な見方と、「四日間の許されない愛に真摯に向き合った中年男女の大人の恋物語」という肯定的な見方である。観終えて、個人的には後者の立場に立っていた。
アイオワ州の片田舎の「屋根のある橋」を撮りに来たカメラマン・ロバートは、そこで平凡な農場主の主婦フランチェスカと出会う。世界を股にかけて冒険に富んだ人生を独りで生きるロバートと、イタリアから夢を抱いてアメリカに渡ったものの野良仕事と子育てに明け暮れる現実に鬱屈した日々を過ごすフランチェスカ。その二人が出会い、一気に恋に落ちるのは必然だったかのように物語は展開する。そして別れの四日目を迎えて二人は葛藤する。家や家族を捨ててロバートと出ていくことを、最後にフランチェスカは断念する。
掟にとらわれない孤独で緊張感に満ちた人生と、日常の様々なルールや倫理観に身をゆだねながら平穏で安定した人生・・・。ロバートとフランチェスカの背負った人生の葛藤は、一人の人間の内にある葛藤でもある。だからこそ人間は興味が尽きないし、人生は奥行きが深くて愉しい。そうしたテーマを観るものに提示し、判断を委ねたこの作品に共感をしたのだ。「不倫を美化した作品」と切って捨てられない人間の奥深い葛藤のドラマとして受け止めた。
撮影当時、ロバート役のクリント・イーストウッドは今の私と同年代の65歳だったという。かってのマカロニ・ウエスタンのヒーローは初老の魅力的なカメラマンを見事に演じていた。それ以上にフランチェスカ役のメリル・ストリープの肉感的で魅惑的な演技に思わず感情移入してしまった。テーマ性には二分される評価も、二人の演技には誰もが及第点を与えていた。
この作品が取上げたテーマについての評価は大きく分かれている。「単に不倫を美化しただけの作品」という否定的な見方と、「四日間の許されない愛に真摯に向き合った中年男女の大人の恋物語」という肯定的な見方である。観終えて、個人的には後者の立場に立っていた。
アイオワ州の片田舎の「屋根のある橋」を撮りに来たカメラマン・ロバートは、そこで平凡な農場主の主婦フランチェスカと出会う。世界を股にかけて冒険に富んだ人生を独りで生きるロバートと、イタリアから夢を抱いてアメリカに渡ったものの野良仕事と子育てに明け暮れる現実に鬱屈した日々を過ごすフランチェスカ。その二人が出会い、一気に恋に落ちるのは必然だったかのように物語は展開する。そして別れの四日目を迎えて二人は葛藤する。家や家族を捨ててロバートと出ていくことを、最後にフランチェスカは断念する。
掟にとらわれない孤独で緊張感に満ちた人生と、日常の様々なルールや倫理観に身をゆだねながら平穏で安定した人生・・・。ロバートとフランチェスカの背負った人生の葛藤は、一人の人間の内にある葛藤でもある。だからこそ人間は興味が尽きないし、人生は奥行きが深くて愉しい。そうしたテーマを観るものに提示し、判断を委ねたこの作品に共感をしたのだ。「不倫を美化した作品」と切って捨てられない人間の奥深い葛藤のドラマとして受け止めた。
撮影当時、ロバート役のクリント・イーストウッドは今の私と同年代の65歳だったという。かってのマカロニ・ウエスタンのヒーローは初老の魅力的なカメラマンを見事に演じていた。それ以上にフランチェスカ役のメリル・ストリープの肉感的で魅惑的な演技に思わず感情移入してしまった。テーマ性には二分される評価も、二人の演技には誰もが及第点を与えていた。
映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」 ― 2013年02月18日
テレビ放映の映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」を観た。7年前に封切られ、大ヒットした第一作「ALWAYS 三丁目の夕日」の第三作だ。1964年(昭和39年)の東京オリンピック開催の年を舞台とした作品である。第一作は劇場で大いに共感し、ウルウルしながら愉しんだ。第二作は残念ながら見逃していた。番組表で第三作放映を知って飛びついた。
やっぱりいい作品だった。もちろん50年前の昭和の良き時代の郷愁もある。個人的にも青春真っ只中の頃の時代風景である。その風景がリアルに再現されて展開する。冒頭の模型飛行機が飛び交うシーンで一気に引き込まれた。竹ヒゴと薄紙で作られたその飛行機は、我々の世代には限りない愛着を思い起こさせるものだ。
この作品の素晴らしさは、単なる郷愁の世界に浸れることではない。50年後の今の社会が失くしたかけがえのないものを浮かび上がらせてくれることこそ、この作品の真価だ。売れない小説家・茶川竜之介一家と自動車修理工場・鈴木オート一家を中心とした夕日町三丁目の住民たちが織りなす物語である。そこで繰り広げられる様々なシーンは、かっての日本のどこにでもみられた「向こう三軒両隣」の風景だ。近所の世話焼きオバサンやオジサンが何にでもイッチョカミする。何かあるとごご近所総出で絡み合う。互いの家にもずかずかと入り込む。一見何とも煩わしい関わりの根底に、助け合い、寄り添い合うご近所の絆が強固に横たわる。
格差社会、ワーキングプアー、無縁社会、孤独死・・・。50年後に私たちが手にした社会のなんと殺伐とした現実だろう。それは、昭和40年代の高度成長、バブル経済とその崩壊、失われた10年、グローバリズムと小泉構造改革、政権交代といった変遷の果ての手にした現実でもある。物質的豊かさを求めて経済成長にひた走った果ての現実でもある。
作中で茶川に向かって妻ヒロミが語りかける言葉が重い。「あなたが、成功して豊かにならなくても、出世して偉くならなくても私は幸せ・・・」。
やっぱりいい作品だった。もちろん50年前の昭和の良き時代の郷愁もある。個人的にも青春真っ只中の頃の時代風景である。その風景がリアルに再現されて展開する。冒頭の模型飛行機が飛び交うシーンで一気に引き込まれた。竹ヒゴと薄紙で作られたその飛行機は、我々の世代には限りない愛着を思い起こさせるものだ。
この作品の素晴らしさは、単なる郷愁の世界に浸れることではない。50年後の今の社会が失くしたかけがえのないものを浮かび上がらせてくれることこそ、この作品の真価だ。売れない小説家・茶川竜之介一家と自動車修理工場・鈴木オート一家を中心とした夕日町三丁目の住民たちが織りなす物語である。そこで繰り広げられる様々なシーンは、かっての日本のどこにでもみられた「向こう三軒両隣」の風景だ。近所の世話焼きオバサンやオジサンが何にでもイッチョカミする。何かあるとごご近所総出で絡み合う。互いの家にもずかずかと入り込む。一見何とも煩わしい関わりの根底に、助け合い、寄り添い合うご近所の絆が強固に横たわる。
格差社会、ワーキングプアー、無縁社会、孤独死・・・。50年後に私たちが手にした社会のなんと殺伐とした現実だろう。それは、昭和40年代の高度成長、バブル経済とその崩壊、失われた10年、グローバリズムと小泉構造改革、政権交代といった変遷の果ての手にした現実でもある。物質的豊かさを求めて経済成長にひた走った果ての現実でもある。
作中で茶川に向かって妻ヒロミが語りかける言葉が重い。「あなたが、成功して豊かにならなくても、出世して偉くならなくても私は幸せ・・・」。
映画「ライフ・オブ・パイ--トラと漂流した227日--」 ― 2013年02月14日
昨年の夏に、我が家に3D機能付46型液晶テレビとディスクレコーダーが導入された。以来、DVDレンタルやテレビの映画番組や録画を観ることが多くなり映画館から足が遠のいた。ところが昨日の午前中、労働委員会の斡旋を終えてから夕方5時の定例会までポッカリ空白時間ができた。そこで久しぶりに映画館に足を運んだ。どうせなら映画館ならではの作品を観たいということで選択したのが「ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日」だった。3Dの美しい映像を迫力ある大画面で堪能できるという期待があった。
結論から言うと「期待外れ」の感が拭えなかった。様々な要因があるが、上映館のTOHOシネマズ梅田のスクリーンが小さかった点が大きい。封切り後20日以上経過し小型スクリーンでの上映に移行していたためだ。最後部の座席だったこともあり、3Dの迫力が減殺された。次にストーリー展開での共感に乏しかった。「トラと漂流した227日」という衝撃的なプロットをどのように映像作品化するかは脚本家の領分なのだろうが、物語性としては単調に過ぎドラマ性に欠けた。テーマ性についても宗教的な問いかけや野生との共存などが提示されるが、いずれも表面的で心の襞に沁みるものは希薄である。とはいえ、映像美だけは文句なしに愉しめた。とりわけさまざまに変化する大海原の映像は3D効果をいかんなく発揮し迫力に満ちたものだった。もうひとりの主人公ともいうべきベンガル虎・リチャード・パーカーの堂々たる媚びない演技(?)もまた秀逸だった。
結局、この作品を通じてあらためて痛感したのは、映画は総合芸術だという点だった。観客が対面するスクリーンのサイズは映画の作り手には無縁の世界である。それでも観る側はそれすらも作品の評価に込めてしまうものだ。原作、脚本、監督、カメラマン、俳優、CG技術、道具や美術、衣装、上映環境など様々な人々が織りなす総合芸術としての映画作品を鑑賞する自身の総合力もまた試されている。
結論から言うと「期待外れ」の感が拭えなかった。様々な要因があるが、上映館のTOHOシネマズ梅田のスクリーンが小さかった点が大きい。封切り後20日以上経過し小型スクリーンでの上映に移行していたためだ。最後部の座席だったこともあり、3Dの迫力が減殺された。次にストーリー展開での共感に乏しかった。「トラと漂流した227日」という衝撃的なプロットをどのように映像作品化するかは脚本家の領分なのだろうが、物語性としては単調に過ぎドラマ性に欠けた。テーマ性についても宗教的な問いかけや野生との共存などが提示されるが、いずれも表面的で心の襞に沁みるものは希薄である。とはいえ、映像美だけは文句なしに愉しめた。とりわけさまざまに変化する大海原の映像は3D効果をいかんなく発揮し迫力に満ちたものだった。もうひとりの主人公ともいうべきベンガル虎・リチャード・パーカーの堂々たる媚びない演技(?)もまた秀逸だった。
結局、この作品を通じてあらためて痛感したのは、映画は総合芸術だという点だった。観客が対面するスクリーンのサイズは映画の作り手には無縁の世界である。それでも観る側はそれすらも作品の評価に込めてしまうものだ。原作、脚本、監督、カメラマン、俳優、CG技術、道具や美術、衣装、上映環境など様々な人々が織りなす総合芸術としての映画作品を鑑賞する自身の総合力もまた試されている。



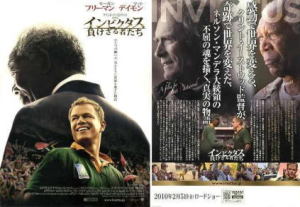


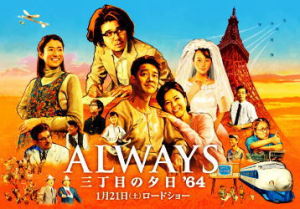

最近のコメント