乙川優三郎著「五年の梅」 ― 2017年04月12日
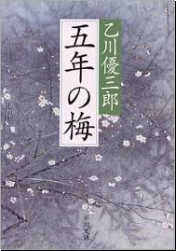
乙川優三郎の短編集「五年の梅」を読んだ。五篇の短編がおさめられている。どの作品にも共通しているのが不幸のどん底にあえぐ主人公たちが追い詰められながらも最後の土壇場で踏みとどまり、生き直す力を取り戻す姿である。生きることに不器用な、あるいは下劣な生き方しかできない人物たちにスポットを当て、ギリギリのところで生き直す機会を与えている。解説でも指摘されているように、それは作者・乙川優三郎の優しさなのろう。その優しさに魅かれ浸されながら読者は乙川ワールドに引き込まれていく。
そうした主題の醍醐味とは別に、作者の情感溢れる表現力に圧倒されたのが表題作の「五年の梅」だった。慕い合い暗黙のうちに将来を誓い合っていた助之丞と弥生。助之丞は弥生との別れも決意して主君に諫言し蟄居の身となる。募る想いを振り切って嫁いだ弥生は婚家の惨酷な家風と誕生した盲目の娘の養育という苛酷な境遇に晒される。蟄居を解かれ出仕した助之丞は幾度も弥生に救いの手を差し伸べるが頑なに拒否される。それでも助之丞はようやく主君お抱えの眼医者の診療を弥生の娘に受けさせられるところまでこぎつける。
眼医者の薬園の梅林に向かう道筋で助之丞は弥生母子と出会う。道なりを歩きながら泥濘が道を塞いだ時、助之丞は娘を抱き上げて渡してやる。弥生にも手を貸そうとして振り向く助之丞。以下は最後の三行の描写である。
「鮮やかな紅梅の向こうに歩いてきた道のりが見えて、胸のつまる気がした。その案外に長い道のりの終わりに弥生はうつむいて両手を握りしめていたが、助之丞が泥濘から手を差し出すと、震える手を伸ばしてきた」。頑なに拒否してきた弥生が意を決して受け入れた瞬間の鮮やかで余韻の籠った描写だった。
そうした主題の醍醐味とは別に、作者の情感溢れる表現力に圧倒されたのが表題作の「五年の梅」だった。慕い合い暗黙のうちに将来を誓い合っていた助之丞と弥生。助之丞は弥生との別れも決意して主君に諫言し蟄居の身となる。募る想いを振り切って嫁いだ弥生は婚家の惨酷な家風と誕生した盲目の娘の養育という苛酷な境遇に晒される。蟄居を解かれ出仕した助之丞は幾度も弥生に救いの手を差し伸べるが頑なに拒否される。それでも助之丞はようやく主君お抱えの眼医者の診療を弥生の娘に受けさせられるところまでこぎつける。
眼医者の薬園の梅林に向かう道筋で助之丞は弥生母子と出会う。道なりを歩きながら泥濘が道を塞いだ時、助之丞は娘を抱き上げて渡してやる。弥生にも手を貸そうとして振り向く助之丞。以下は最後の三行の描写である。
「鮮やかな紅梅の向こうに歩いてきた道のりが見えて、胸のつまる気がした。その案外に長い道のりの終わりに弥生はうつむいて両手を握りしめていたが、助之丞が泥濘から手を差し出すと、震える手を伸ばしてきた」。頑なに拒否してきた弥生が意を決して受け入れた瞬間の鮮やかで余韻の籠った描写だった。

最近のコメント